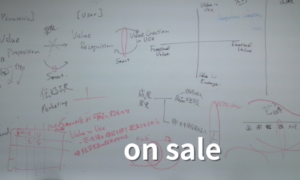名称は大切、それに相応しい内容にすることはもっと大切
横断歩道と優先座席
【2010年5月記載】
単身赴任先のマンションから会社までは、歩いて30分かかる。歩道は比較的幅が広く、ゆったりと歩けて安心で快適だ。しかし、歩道のないところが少しあり、そこでは車道を歩くことになる。昼間はよいのだけれど、夜間ともなると、照明は不十分で、最近の流行で服装も黒っぽいものだから、危なっかしいと言ったらこの上ない。たまに脇を通り抜ける車にヒヤリとすることもある。
先日、奈良の自宅付近で、夜間横断歩道を渡っている人が、車と接触し、そのまま車に巻き込まれて亡くなられるという事故があった。すると一週間もしないうちに、全く同じところで、同じような事故が起こった。幸いこのときは怪我程度ですんだようでよかったのだけれど、あまり人通りのない、住宅街の中でこのような事故が続いたので、少し心配になった。対策として何がとられたのか。横断歩道の白線をより分かりやすくなるように塗りなおしたことと、横断歩道の周りの照明をより明るくしたこと。対策としては、なんとなく頼りなさそうに思えるのだけれど、私の経験から推し量ると、夜間では黒っぽくて分かりにくい人影が、これではっきり見えるようになるので、対策としてはベターと言えそうだ。
横断歩道の役割をまともに考えたことがなかったのだけれど、安全への配慮という点で見直してみると、意外と安全への配慮がなされていて、それなりに横断歩道を使う意義はあるようだ。まず、横断歩道には信号が付いている場合が多い。また、比較的見通しのよいところに設けられている。そして、白線が敷かれ、照明器具も付いている。そこを通行する人が認識されやすいような工夫がある。道路を横断するときは、横断歩道を使うのが安全だ。横断歩道は横断するための歩道であって、その名に相応しい安全への配慮や工夫が凝らしてある。
その点、電車に設けられている「優先座席」は名ばかりで、実体が伴っていないのではないかと思ってしまう。第一、お年寄りや体の不自由な人が座っていないし、また座りたい様子もない。年寄り扱いされるのがいやなのかもしれないが、そこに座る意義が見出せないのではないだろうか。優先座席でなくても、普通の座席が空いていればそこで良いし、優先座席に座っている人を押し退けるようにしてまで座る価値もないように思える。
これもその名称にふさわしい工夫をすれば、ぐっとその意義が高まるのではないだろうか。優先座席には、手摺りの数を増やすとか、座席に自動昇降機能をつけるとか、まぶしくないように窓を磨りガラスにするとか。そうすれば、実際に座りたくなるし、体も楽になる。若い人だって、見た目が違うのだからそれなりに考えて、年寄りに配慮はするだろう。優先座席の使われていない実態を、単なる気遣いとか道徳心の欠如といった精神論で片付けてしまうのでは、それこそ思慮が足りないというものだ。
私は、いつも、ルールはそのまま守っても面白みがない。無視してこそ新しい発見があると考えてきた。しかし、ルールは何のためにあるのかをもう一度よく考えて、行動する必要がありそうだ。闇雲に、天邪鬼を通しても、そこには何の意味も意義もないことがたくさんありそうだ。