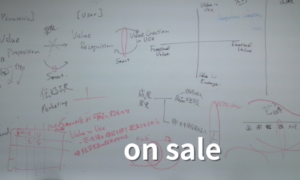ビジネスで必要な直観力を養うには"絵"を見ることだ!
美術館について
【2012年6月記載】
博物館と美術館、どちらもMuseumである。しかし、私たちはこれを切り分けて表現している。私の解釈としては、博物館とは、自然科学資料や考古学・美術・歴史的な遺物などを集めて、分類し、保管した施設のことをいっていると思う。その中で、美術品に特化して展示したものを美術館といっているのではなかろうか。特だしして美術館という名称を付けているのだから、それほどまでに美術品は私たちの感性を揺さぶるもので、興味を惹く対象なのであろう。
出張でいろいろな都市に行っているけれど、美術館の数は圧倒的に東京が多い。主なものでも20~30はある。それに比べて関西は少ない。大阪、京都、神戸を合わせても10ヶ所程度である。地方都市にも必ず美術館の1つや2つはあるので、出張の際にはそれなりに楽しめるのだが、東京のそれに比べれば量的にも質的にも見劣りがする。さほど東京の魅力には凄いものがある。欧州の主だった都市も歴史的な素晴らしい美術館を数多く抱えているけれど、東京もそれに匹敵していると思う。東京は美術を楽しめる素晴らしい都市なのである。
ここ数年、特にこの2、3年は東京出張も多く、ほとんど毎月のように訪れる機会がある。そしてその度に努めて美術館に足を運ぶようにしている。
絵画を鑑賞する時、いい絵とは何か。どんな絵が素晴らしいと言えるのか。はっきりとした指標はないと思う。その絵を観て、「あっ、いいなぁ」とか「うっ、凄い」という印象が持てればそれでよいと思う。以前は、とっても有名な絵であるとか、あの著名な画家が描いた絵だからとか、教科書に載っている絵だから、といった評価指標でもって、絵画を眺めていたのだが、最近になってようやく感覚的に、その絵の素晴らしさというものを掴めるようになった。もちろん、私にも好みがあって(もしかしたら偏っているかもしれない)、必ずしも第3者の同意が得られるとは思ってはいないけれども。
若い頃は、印象派の絵が馴染みやすく、美しいと感じていたのだけれど、暫くするとゴッホのあの筆遣いというかタッチにグッと惹きつけられるようになったし、ピカソの色遣いも美しいと感じるようになった。ユトリロの描く街並みも自然と湧き出てくるようなダイナミックさがあって美しい。岸田劉生の「道路と土手と塀」の力強さには圧倒された自分を見つけてびっくりした。最近では絵の持っているエネルギーもしくは躍動感というようなものに惹かれるようになった。国吉康雄や片岡球子の絵には生きているうねりのようなものを感じるし、このような日本人の絵画に接すると嬉しくなる。生きているという実感を覚え、確認するためにも、美術を鑑賞することは意義のあることであるし、この感覚こそが新しいものを創り出すエネルギーになるのではないかと考えている。
美術館の入場料は一人1500円程度で、必ずしも安くはない。出張時に訪れることが多いので、自ずと平日となる。平日と言っても入場者は多く、好みの絵の前でじっくりと鑑賞できるとは限らない。人気の企画展示会の場合には、一時間程度並んだことも何度かある。入場者のほとんどが年配者で、特に女性が多い。人が多いということは良い事なのだけれど、あまりにも年寄りが多く、若い人たちもしくは私たち中年層が少ないのは寂しい限りで、如何なものかとも思う。
私が一番気に入っているのは、上野にある国立西洋美術館。企画展も見応えのあるものが多いのだけれど、常設展が充実していて、訪れるたびに新しい発見がある。同じ絵画でも、その時々に、訪れる私の心境によって違うのか、随分と受けるインパクトが異なる。奇異に感じていたピカソの絵が、突然、色鮮やかに目に入ってきたり、ボーッとした印象しかなかったモネの絵がとてもクリアに見えたり、今まで嫌いだった宗教画に非常な美しさを感じたり...。いつ行っても、楽しく面白い、充実したひと時を過ごすことができる。同様に国立博物館の常設展示も素晴らしい。ここでは絵画だけでなく、陶器、漆器、屏風、衣装、刀剣、甲冑、仏像などなど、まさに博物館としての美を堪能できる。
やっぱり東京は日本の中心。東京は何でも好きなものが味わえる魅力に溢れている。