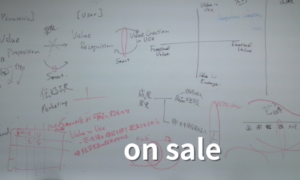ルールは理性の賜物だね
勝率と勝ち点
【2017年6月記載】
仕事での疲れを癒すのに、また日々の生活で溜まったストレスを解消するのには、スポーツ観戦が一番である。贔屓のチームや好きなアスリートが、勝ったり活躍してくれると、我がことのように嬉しくなって、疲れやストレスが一気に吹っ飛んでしまうような気分になる。ただし、負けてしまうとその逆になってしまうこともあるので、必ずしもスポーツ観戦が精神面での特効薬になるとは限らないのだけれど。
よく見るスポーツ、特に興味があるスポーツは、誰もがほとんど同じとは思うけれど、サッカーと野球である。ガンバ大阪は創設以来の熱心なファンであるし、広島カープは我が家の地元球団であり少なからず縁もあるので、これまた熱烈なファンだと認識している。しかもこの2つのチームは、近年、いずれも優勝争いの中心にいるので、日々のゲーム結果が気になって仕方がない。
ところで、このゲームの勝ち負けの考え方に、正確には「優勝」の定義の仕方に、少し違いがあるのに気がついた。優勝は何によって決めるのか。
プロ野球では、勝率の高いチームが優勝となる。そして勝率とは、勝利数÷(勝ち数+負け数)であり、分母に引き分けは入らない。だから144試合を戦って、1勝143分けだと、勝率100%となって、優勝となる。勝ち数が多い場合は、引き分けは勝ちに近いということになる。
一方、サッカーはというと、これは勝ち点の多いチームが優勝となる。勝つと3、引き分けだと1、負けは0ということで、この合計点の多いチームが優勝となる。だから引き分けは負けに近いということになる。競技によって引き分けの持つ意味が違う。
例をあげてみる。5試合戦って、3勝1敗1分けのチームAと、1勝0敗4分けのチームBとでは、どちらが優勝となるのか。
勝率で決める場合は、勝率1.00のチームBが、0.75のチームAを上回って、チームBの優勝となる。勝ち点で決める場合は、勝ち点10のチームAが、7のチームBを上回って、チームAの優勝となる。
どちらの決定方式に賛同するかは、人によって違うだろう。3つ勝ったチームがすごいと思うか、1つしか勝たなくても負けなかったチームがすごいと考えるか。
野球とサッカーでは、ゲームを構成するメンバーや攻守の切り替わり方が違うし、ルールの複雑さも違う。そして得点のカウントや勝敗の決まり方も違う。サッカーは点が入りにくいゲームであり、戦術的に引き分けを狙うことが可能だ。しかし、野球は点が入りやすいゲームであり、引き分けに終わることは少ない。また、ピッチャーの出来不出来にとても左右されやすく、ディフェンス力の高いチームが勝つ確率が高くなるのではないかと思っている。
ゲームは勝ち負けがはっきりしないと面白くない。その点で勝負のつきにくいサッカーは、引き分けをできるだけしないようにすべく、引き分けの価値を低くしているといえる。一方で、点が入りやすく、比較的勝ち負けのつきやすい野球は、引き分けの扱いに注力しなくても良いのだろう。
ところで、サッカーはオフェンスの力がポイントとなり、野球はディフェンスの力がポイントになる。野球の場合、本当にディフェンスを重視するならば、先発投手が勝ち投手の権利を得る5回まで投げるという概念を捨て、打順がひと回りして打者が有利になる前に交代するという戦術もあるのではないかと思っているのだが、それを実現してくれるチームは今のところいない。
もし、野球の勝率を、勝利数÷(勝ち数+負け数+引き分け数)とすると、引き分けは負けに等しいことになり、先のチームAが優勝ということになる。つまりオフェンス力をより強化していく戦略が取られることになる。そしてもっともっとすごい点の取り合いがみられることになるだろう。
勝率の定義を変えるだけで、ルールを少し変更するだけで、その競技やゲームのあり方が変わってしまう。
考えるに、スポーツとは戦争の代わりであり、人の闘争心を害のない形で満たしてくれる娯楽である。そして、人間が勝手に作ったルールの中で競うものである。勝ったとか負けたとか、優勝したとかできなかったとか、私たちはそれにこだわり一喜一憂する。それが私たちの欲求を満たし、ストレスを解消してくれるものだから。
ルールがあってのスポーツで、それがいい加減なものであったり、なければ、それは戦争になってしまう。