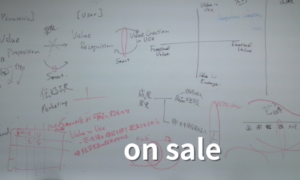14年前の震災直後に感じたことが少しも進んでいない。技術への投資をもっとすべきだ...
環境意識
【2011年6月記載】
早稲田大学のT先生のところにお伺いした。先生の専門は住環境であり、欧米の動向を中心に、各国の環境政策と企業動向に関して情報交換をさせて頂いた。情報交換というよりは一方的に教えを乞うたというべきかも知れないが。
私たちが考えていることは、当然世の中のトレンドの域を出ないでいることは認識しているつもりだけれど、世の中の流れは速い。HEMSに関しても、韓国メーカーを中心に次から次へと新しいモデル住宅が出てきているし、スマートメーターによるエネルギーの見える化(カーボンフットプリント)は、アメリカで大規模に展開されている。その現状をつぶさに見せ付けられて、私たちの動きの遅さ、もしくは独創性の足りなさを考えさせられた。
そういったグローバルでの動きを知るとともに、一方で、この震災以来、日本のエネルギーに対する考え方が大きく変わっているのが分かった。電力に対する意識である。特に関東圏において。
震災前は何と言っても「オール電化」であった。オール電化こそがCO2低減に効果があり、安全で、コスト的にも優位であり、化石燃料を使うのは時代遅れであるという風潮が世の中を支配していた。ところが今や、エコキュートを買いたいと口に出すことは憚られ、IHクッキングヒータは売れもしない。単に電気を使う機器だというだけで。この電力の逼迫している状況で、新たに電気を消費する機器を購入するということは罪悪なのである。
また、原子力のリスク(放射能汚染)を無くすために、原子力発電を削減し火力発電に置き換えていくという動きは、新たなCO2増加を助長するものであり、決して地球環境にはよくない。先生の話では、今後、必然的に原単位は上がり、原子力を補うだけの再生可能エネルギーの活用はできないという。全くもって今までのトレンドとは明らかに違う。まさに逆方向である。
オール電化がダメなのであれば、当然、電気自動車もNGのはずである。電気自動車も電力消費量は大きい。ところが、先生は、電気自動車は今後伸びると予測されている。マーケットの声がそうなのである。この震災で、人々はガソリンの供給不足に辟易したようなのだ。どこに行ってもガソリンが無い。したがってガソリン自動車は役に立たない。でも電気自動車は何時だって充電できて、便利そうだ。要は、理論でどうのこうの言ってもダメなのだ。心理的要素で物事は決まるようである。停電になれば、電気自動車は役に立たなくなるのに。
今や、環境問題といえば、放射能汚染なのである。CO2が少しくらい増えても良いのである。CO2が増えて温暖化が進もうとかまわない。今大事なのは、原発を無くすことなのである。温暖化が進み、いくら猛暑日が続こうが、しばらくは我慢しなくてはいけない。できるだけ電気は使ってはならない。電気を使わないことはCO2削減にもつながるのだから、とにかく我慢するべきなのだ。
放射能は嫌だ。だから原発は廃止する。けれど快適性は保ちたい。だから多少CO2が増えてもかまわないので、化石燃料を使おう。とにかく今の生活は守りたい。なんと刹那的な!
私は思った。「電気を使わずに快適にする」、「使い勝手の悪い再生可能エネルギーを効率的に活用する」、このような課題(二律背反)を打破できる可能性があるのは、やはり技術なのではなかろうか。技術者がんばれ。