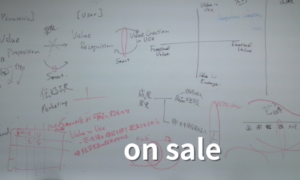10年前も今も思う。できない奴に救われることは多々ある
教訓 その2
【2014年3月記載】
60年近く生きてくると、ものごとを長いスパンで見る力がついてくる。目先の利益で動くことの無意味さを知るとともに、その時不利益であったとしても後々必ずしもそうではなくなってくることなど、若い時には理解できなかったことが、分かってくる。
幼い頃、小学生の頃だったろうか、おやつの多い少ないでしょっちゅう兄弟げんかをした。学校の掃除当番をしたとか怠けたとかで、同級生と取っ組み合いの大喧嘩をした。得したとか、損をしたとか、あいつは怠けているのになぜ叱らないのか、先生に食って掛かっていつも怒られてばかりいた。それは大学を卒業し、会社に就職しても、私の根っこのところは何も変わっていなかった。自分がこれだけ頑張ってやっているのに、一方では何もせずに、恩恵にあずかっている人間がいると思うと、無性に腹が立った。頑張っただけ、成果がでた分、他の人よりも多く仕事をした分、それ相応の報酬を得るのは当然だと思った。できる人間は、できない人間よりも多くもらうのは当たり前だと。その考え方は常識だと思う。世間一般の通念だと思う。けれど、今になって思うに、果たしてそう言ってしまって本当によいのだろうかと。
計算の速い人は、そうでない人の2倍も3倍もの量をこなすだろう。セールスの上手な人は、人の何倍もの商品を売ることができるだろう。しかし、計算の速い人に比べて、そうでない人は怠けているのだろうか。セールスをする人は誰もがその人なりに一所懸命努力しているのではないのだろうか。結果として、あまり多くは売れなかったとしても。
確かに仕事のできる奴は、できない奴の何倍もの成果を出してくれる。できない奴はみんなの足を引っぱるばかりで、ほとんど何も生み出さないのではないかと思えるくらいに、できない。
それでは、できる奴ばかりで仕事をしたら、それで十分ではないかと考えるけれど、本当にそうだろうか。できる奴が10の仕事をする間に、できない奴は2~3しか仕事をしないとしても、トータルでは12~13の仕事をしたことになる。また、12、13でその仕事が完成するとなると、10では完成したことにならない。2~3があって、成り立つことになる。それにその2~3は、10とは質の違うものだから、できる奴にとっても参考になるはずで、後々の仕事に活きてくるはず。できない奴がいてこそ、できる奴の自尊心が満たされ、モチベーションが上るという面もあるので、できない奴はできる奴の下支えをしてくれてもいるともいえる。
具体的に問われるのは、報酬の多寡や評価の良し悪しであるけれど、能力の差が歴然としている場合はほとんど給料や昇格に反映されているので、とやかく目くじらを立てることもない。できない奴の報酬が成果に比べて多いと思われることもあるだろうけれど、生きていくためにはみんなで分かち合うことは必要だ。できない奴よりできると思っている自分の報酬が少なくなければ、それでいいじゃないか。
何にもまして重要なことは、長い人生で見ると、できる奴が10ほど頑張った分は、それが自分の身になっている、力になって生きる力が強くなっている。できない奴に知らず知らずのうちに育てられている。頑張った分は返ってくる。それに2~3の力しかないと思っていたできない奴に救われることも多々ある。なにしろ自分とは違う人間なのだから、自分にないものを持っている。それがとてつもなく少なくても、自分にないものは貴重だ。それに助けてもらうことがあるから不思議だ。
自分の力を100%出した人生は充実している。そして楽しい。評価はどうだの、報酬が足りないなど、文句はたくさんあるだろうけれど、自分の人生を力いっぱい生きることの方がとても大事で、幸せだ。