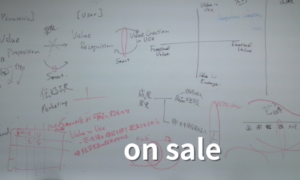闇と光、二つとも現実を覆い隠すものであり、私たちはそれによって救われている...
イルミネーション
【2015年12月記載】
この季節になるとクリスマスイルミネーションが華やかになってくる。特に近年はLED技術の普及もあってか著名な施設をはじめ、繁華街、住宅街、ストリートなどそこら中に光のイルミネーションが溢れている。大阪でも中之島や御堂筋沿いは、カラフルな光で街が輝いている。
クリスマスでも、昔はもっともっと地味だった。クリスマスツリーにランプがともれば、それだけでとても眩しく見えた。およそ電球というものがそこそこの値段がしたし、電飾で街を飾るという考え自体、コスト的にも無謀であった。それが豆電球の普及により、またここ数年ではLEDランプにより、コスト的にも耐久的にもそしてデザイン的にも実現していくハードルは低くなった。誰でも簡単にできるようになった。
ところで、どうしてみんなが一斉にイルミネーションの豪華さを競うようになったのだろう。照明技術の発達とともにくらしにゆとりができてきて、生活の中にも新たな楽しみを見出そうとしているのだろうか。よく言われる話だけれど、物質的な欲求からソフト的なもの、文化的なものへの欲求に移行してきているのは明らかだ。モノを買い求めた時代は過ぎて、くらしの中に精神的な満足を求めている。そもそも今の時代にあっては、モノ自体はいくらでも手に入るのであって、もはやモノで欲求を満たそうとするのは困難となってきている。モノを買って欲求を満たすとしても、ブランド品を買ってしまうといった具合にモノの機能を求めるのではなく実際にはブランドというソフトを買っているのであって、モノにコストをかけているのではなくなっている。
くらしの中に楽しみを見つけようとしている今、イルミネーションは非日常的なものを手軽に提供してくれていて、有り難い存在となっている。
なぜ、今この時期に、イルミネーションが持て囃されるのだろうか。クリスマスの飾りつけという意味合いなのか。冬でなくて、夏にしてもいいのではないのか。寝苦しい夜をイルミネーションで吹き飛ばす。夕涼みではないけれど、アウトドアでの催し物は夏の方が良いように思える。歴史的にクリスマスシーズンを灯りで飾るというのがあり、それが進展して今日のような派手な電飾のイルミネーションへと変化していったのだろうか。
今の時期の夜は長い。その長い夜を光り輝くイルミネーションで飾り付けることは、暗く沈みがちなこの季節に人々を元気付けるという意味合いはおおいにある。特に欧米の冬は長いし、暗くて寒い。だから省エネでとてもカラフルな今のイルミネーションの私たちに与える効果はとても大きいし、それを楽しみにしている人も多い。
先日、大阪中之島へイルミネーションを見に行った。夕方5時くらいから薄暗くなり、5時半にはほとんど闇夜に包まれた状態になった。大阪市役所から中央公会堂にかけての通りは、すでに煌びやかな光のイルミネーションが映えるような状態になっていた。時間的にはまだ早いのだけれど、イルミネーションアーケードはすでに人の波で溢れかえっていた。中央公会堂ではプロジェクションマッピングが開催されていて、光と音のファンタジックなストーリーが展開されていた。一見の価値はあり、私の気持ちは昂った。
イルミネーションの人気が高いのは分かる。人々が集まるのも分かる。寒いこの時期に、輝きを求めてみんなが集まってくる。別に信仰心があるとは思えないし、見たからと言って特に自慢できるものでもない。ただ普段とは違う雰囲気に浸りたいがために、それがとても安価(無料)で体験できる。ただそれだけではないのか。
年々規模が拡大し、豪華絢爛になっていく街角のイルミネーション。今の庶民にとっての一番の楽しみがこのイルミネーションだとしたら、少しばかり物悲しい。