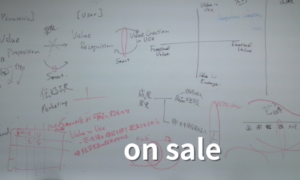言葉は考えるツールである分、ものごとを決定づけてしまう魔力がある
言葉の力
【2016年3月記載】
もう随分とむかしのこと。ほとんど勉強らしい勉強をしていなかった大学の教養課程ではあったが、いくつかの講義の内容は覚えているもので、今もって自分でも良く覚えているものだと感心することがある。高校を卒業したばかりの、受験勉強しかしてこなかった世間知らずの若者達に、いきなりレベルの高い専門的な内容の話を、分かりやすく教えるのはとても難しいものであるけれど、少しでも記憶に残っていたということは、それだけ先生の講義が素晴らしいものであったということかもしれない。
そのような記憶の中のひとつに、言霊(ことだま)に関する講義があった。十分理解できないまでも、言葉の力にふれるもので、当時の私にはとても印象が強かった。今でも、大教室の黒板に先生が言霊の説明を板書していく様がありありと浮かんでくる。日本の古代では、言葉に霊があり、一旦言葉にするとそれにはある種の力が備わっているものと信じられていた。そんな内容の話であり、このような講義が延々と続いたと記憶している。言葉とはそういうものだと。
思っていた事、考えていた事をいちど言葉で表してみると、「意外だったなぁ」と思うことが時々ある。正確に言えば“文章”にしてみることなのではあるが。
頭の中でいろいろと思いをめぐらせているとなんだかとても凄いこと素晴らしいことのように思えていた事柄が、いざ文章にしてみるととても浅薄で中身のないものであったり、逆に頭の中では整理できないままでいた事が、言葉や文章にすると思ってもみなかった結果につながったりと、言葉は表すことにより、それ自身が私に新しい知見をもたらしてくれることがある。言葉には力があると思う。
言葉は他者に自分の意見や思いを伝えるツールであるけれど、つまり情報伝達の素晴らしい手段であることの他に、自分自身を形づくるものでもあると思う。言葉を発することにより、相手に自らの気持ちを伝えることになるが、それと同時に、言葉にするためには自らの考えをはっきりさせなければならない。言葉にすることは、自分自身の中にある曖昧なものや不確かなものを振り払い、きちんと意思を形作る作業をすることなのである。言葉は、言葉を発する人と言葉を受け取る人の間に、共通の情報を植えつける道具なのであるから、それなりによく考えて、よく選択して、発しなければならない。
先日、親会社のS参与と当社の社長の三人で、主要取引会社の法務部門を訪問した。その後、S参与が草津の事務所に立ち寄りたいというので、事務所にて三人で情報交換をした。そして、契約関連の業務にまつわる話題の中で、私の部下のI社員の話しになった。S参与曰く、
「各事業部、各支店の担当者とメールや契約書等のやりとりをしているのだけれど、その中でI社員が一番しっかりしている。資料も間違いがほとんどなく、信頼できる」
私にとっては、思いもかけない嬉しい言葉であった。彼女はそう言って、その言葉に自ら頷くようにしてそれを繰り返した。当社の社長もそれを聞いて、感心した様子であった。
この光景を見て、私ははっきりと感じてしまった。S参与は話の中で、I社員の事を思い出し、そういえば彼はこんな人間であったなぁと、つい口をついて言葉に出してしまった。上司である私に対するリップサービスもあったかもしれない。とにかく言葉にしたことで、あらためてそれを確認しながら、自分の評価として確定してしまった。それを聞いた社長は、彼の評価を自分の中で定着させてしまった。こんな空気が、その時に流れていたように思う。(事実、この後、社長のI社員に対しての信頼度は格段に増していった)
ある種の雰囲気の中での言葉のやり取りは、その中にいる人たちの心を決めてしまうおそれが多分にある。今回はいい方向であったから良かったものの、言葉には極力気をつけなくてはいけない。言霊だから。