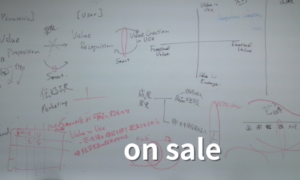我々大衆は猿のようなもの...未来を照らす情報はネットからしか得られないのが現状だ
朝三暮四
【2010年11月記載】
今年の初め、当時の鳩山総理が衆院予算委員会で、朝三暮四と朝令暮改の意味を取り違えて話題になったが、この朝三暮四という言葉の解釈はとても難しいと思う。高校生の頃、漢文の授業で習ったのだけれど、その意味するところが全く理解できなかったことを覚えている。
宋有狙公者,愛狙,養之成群,能解狙之意;狙亦得公之心。損其家口,充狙之欲。俄而匱焉,將限其食。恐眾狙之不馴于己也,先誑之曰『與若芧,朝三而暮四,足乎』、眾狙皆起而怒。俄而曰『與若芧,朝四而暮三,足乎』眾狙皆伏而喜。(列子)
辞書によると「目先の違いに気をとられて、実際は同じであるのに気がつかないこと。また、うまい言葉や方法で人をだますこと」とある。目先の違いというのが理解しにくく、朝と夕を言葉の中で表現しているのに、猿は朝のこと(目先のこと)しか理解できていなかったと解釈すれば、少しは分かってくる。
ものごとをどれだけのスパンで考え行動できるかが、その人の、もしくは組織の性格や特長そして価値を決めるといえるのだろうか。
先日、インダストリー営業のTさんと事業戦略に関して話をしていたのだが、その中で、インダストリー営業では、お得意様たとえばソニー、シャープ、東芝、キャノン、富士通に対して、それぞれに専任をおいて、その人が入社した時から一貫して、ひとつの会社を担当する仕組みになっているという。そうすることによって、相手先の同世代の社員と懇意になれるらしい。そして、相手先の社員が時を経るにしたがって、課長、部長、役員へと昇格していくことにより、当社のアドバンテージが自ずと高くなっていくという考えである。10年、20年もしかすると30年先を読んだ営業活動をしていることになり、社内では、ミスター・ソニー、ミスター・シャープと呼ばれる人たちが活躍していくこととなる。どれだけ先を見た商売ができるかが、ポイントとなっている。
一方、白物家電分野は、どれくらいのスパンで業績を見積もっているのであろうか。洗濯機や冷蔵庫を製造しているビジネスユニットでは、どう考え、ものづくりや人材育成をしているのであろうか。おそらく、3年がひとつの目安ではないかと考えられる。何故ならば、白物家電分野のトップも、各ビジネスユニットの長も、平均の任期は3年程度であり、その3年間の業績で評価されているからである。したがって、何とかこの3年間を増収増益で乗り切りたいという思いが、経営数値にも表れてくる。一般的に、就任初年度は、それまでの悪い部分(負債)をできるだけ吐き出し、リスクヘッジをとり利益はできる限り低く抑える。販売額はなかなか調整できないが、利益はある程度調整できるので、次年度からは、必要最低限の増益になるように少しずつ利益を搾り出していく。3年間を右肩上がりに調整できればしめたものである。それから先はどうなろうと構わない。その時にはもう居ないのだから。
しかし、3年先が読める経営者はまだましな方で、単年度の業績に追われている経営者層も結構居るのが現実だ。そういった部門に限って、方針がぶれたり、その場しのぎの対応に追われていたりして、社員は右往左往するばかりで、経営内容も人材育成も不十分なことが多い。
人生も同じで、どれくらい先を読んで生きているかが、その人の価値になる。刹那的に生きるのがダメだとは言わないが、毎日のくらしに楽しさを見出すだけでなく、生涯を通じての楽しさや生きている価値を見つけることも必要だ。死んだ後のことも考えて、自分の人生を楽しみ、人生の価値を見つけることができたら最高だろうな。