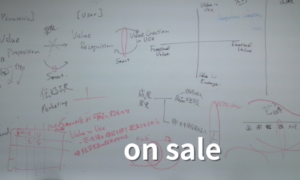情報社会における読書とは何か。読書を考える力に!
読書について
【2014年1月記載】
ショーペンハウアーの「読書について※1」を読んだ。とても良い本だと感じる。私の「読書」というものに抱いている漠然とした感覚を、ロジカルに、分かり易く紐解いてくれて、その感覚とはどんなものだったのかをはっきりさせてくれた。そして、さらにより高い見識でもって、「読書」とはこうあるべきだと私に教えてくれたのである。
「読書は自分で考えることの代わりにしかならない。自分の思考力を他人に預けることであり、自ら考えることはできない。よって、多読に走ると知識ばかりが増えて、自分で考える力が失われる。一貫性を保つことができなくなり、自らの哲学を持てなくなってしまう」
概ね、こんなことが述べられている。決して情報通ではない、また読書もそれほど好きではない私にとっては、とても嬉しい話である。齷齪して情報を収集したり、本屋に入りびたりになるというのは私の性に合っていない。本当に都合のよい話ではないか。
これを私なりに、手前勝手に解釈すると、知識(情報)ばかり増えても何の意味も持たない。単に他人の受け売りになってしまう。それなのに知識が増えたことで、賢くなったと錯覚する。受験などはその典型で、知識があることが賢いことだと思っている。そんなのはナンセンスなのだ。いわんや今の情報社会においては、情報は溢れんばかりであり、しかも情報へのアクセスはとてもスムースだ。こんな状況では知識偏重はますます持って、その意義が薄れるばかりであり、一昔のものしり博士だけでは通用しなくなっているのが現実だ。今とは時代は違うが、それを的確に指摘しているのがこの本であると思う。
確かに知識があればそれだけで生活はできる。しかし、いざという時、環境の変化に対応していくためには、やはり考える力が必要だ。そういった力をつけるためには、情報を上手に使って、自分自身で作り上げ、磨かなければならない。そのために、インプットとしての情報は要る。それは自分の頭の中にきちんと整理され、体系だっていないと有効に使えない。考える力は、自身の思考体系や哲学を持っていないと強いものにはならないし、それを補強するために情報を集めるのである。
守・破・離、習って覚えてまねして捨てる、このようなイメージで読書を捉えるのが一番良いのであろう。「本を読む」→「考える」、「本を読む」→「考える」、この繰り返しで考える力が醸成される。
知識はいくら集めて並べてみたところで、それだけでは何もならない。何も起きない。考える力があってこそ、その知識が役に立つ。知識があることに満足せず、それを越えたところに挑戦するという意識を持ち続けたい。
シュンペーターは、「郵便馬車をいくら並べても、決して汽車にはならい※2」との比喩を使い、イノベーションの非連続性を強調したが、それにも通じるところがあるのではないか。新しいものを生み出すことが今の私のミッションなら、なおさらのことである。
※1 「読書について」 (光文社古典新訳文庫) アルトゥール ショーペンハウアー (著), 鈴木 芳子 (翻訳)
※2 「シュンペーター 孤高の経済学者」(岩波新書) 伊東 光晴(著), 根井 雅弘 (著)