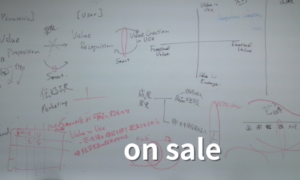「奪うものから分かち合うものへ」企業活動は戦争ではない
シェアについて
【2014年3月記載】
つい最近までシェアといえば市場での商品占有率を指していた。特に私が入社して間もない頃は、シェア何%で、業界No.1であるとか、シェアが何%まで上昇したとか、国内での市場を各社がしのぎを削って奪い合っていた。ランチェスターの法則がもてはやされ、その法則のもとに市場での優位性を確保するための経営戦略を、みんなが考え、実践していた。市場での生き残りをかけてシェアを奪い合っていた。強い者が市場での富や利益を得ることができると信じての生き残り合戦であった。
これはこれで当時としては正しい認識であったと思うし、よりよい商品がより安価にユーザーへ提供でき、私たちは豊かな生活を得ることができた。しかし物が十分に行き渡って、くらしが便利で豊かになった今、どの業界においても、群雄割拠の状態から吸収合併などで、たくさんあった会社は淘汰され、わずかな有力会社のみが生き残った。その結果どうなったのか。
小さな日本という国の中ではそれでもよかった。シェア争いに勝った会社は、その優位性を保ち、売り上げは確保できた。しかし、多くの市場は成長期を経て成熟期を迎え、なおかつグローバル競争の中にさらされ、コスト低減化の努力を余儀なくされた。利益率はどんどん低下して、シェアはあるものの利益は上がらない。商品そのものがコモディティ化した上に、海外生産が増えたことやIT化などにより流通の仕組みも変わってきた。旧来のバリューチェーンが崩れ、海外製品も入ってきたので、単なるシェア争いでは生き残ることや市場での優位性は保てなくなっている。国内でシェアを奪い合っている間に、世の中は変わった。
グローバル化により海外への輸出はもとより、海外からの輸入製品も入ってくるようになり、市場の独占ということは考えにくくなった。加えて、ニーズの多様化に伴い、単純なコモディティ商品の提供だけでなく、生活スタイルや個人の嗜好に合った商品やサービスが求められるようになった。占有率は大事だけれど、それだけで商品やサービスの価値、もちろん企業の価値は測れなくなっている。シェア競争の時代は終わったと考えてもよいのではないか。
ところで最近はシェアといえば、いわゆるシェアすることで、分かち合うことを意味する場合が多い。奪い合うというイメージはない。何でもかんでもシェアリングする。住む部屋も働く場所もシェアするし、自転車や自動車もシェアする。食べ物だってシェアし合うし、服飾品だってシェアする。気心の知れた者同士で、分かち合い助け合うくらし方が広まっている。おそらくお金の余裕がないのが一番の要因なのだろうけれど、余計なものは持たないという合理的な考え方が根底にあると思える。限られた資産(資源)を上手に使って(シェアし合って)、より豊かに上質のくらしをしようというものである。一人勝ちの世界ではない。生き残り戦争ではない。互いに持っているものを出し合ってよりよいものを求めていく共生の世界だ。それには今以上に相手を活かすことが必要となる。互いのよいところを見つけて、それを活かして、お互いが豊かになる。
私たちのめざすあるべき姿の事業とは、このような世界をめざすべきなのではないのか。グローバル化の進展する世の中で、一人勝ちの世界などあり得ない。自分や自社とは何か。他人や他社と比べて何が特長なのか。他社のよいところはどこなのか。他社に足りないところはあるのか。我々のお役立ちできるところを探しあて、そこで頑張る。その中での収支を考える(価値の取り分)。決して大きさ(占有率シェア)は追わない。そういうスタンスが、我々には求められるようになっている。「奪うものから分かち合うものへ」企業活動は、戦争ではない。